基本的な考え方:相続登記等の協力要請文書:作成方法・注意点と専門家(弁護士・司法書士)への依頼方法
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
【相続登記相談事例①】
建物(評価価格:100万円)が(亡)祖父名義で登記されています。相続人は合計10名おりますが、このうち、疎遠な・面識のない・知らない相続人が4名います。
この相続登記を、専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合、弁護士に依頼するのがよいのか、司法書士に依頼するのがよいのかを教えてください。
できるだけ、相続登記にかかる費用を安く抑えたいので、弁護士ではなく、司法書士に依頼したいと考えています。
ポイント:疎遠な・面識のない・知らない相続人との交渉が上手くいくかのどうか
- 不動産の価格:高いか低いか
- 疎遠な・面識のない・知らない相続人:どういう人か
- 交渉する人:本人・弁護士・司法書士の資質(能力・判断力)
- 手紙文の内容
ポイント1【不動産の価格:高いか低いか】
不動産の価格が高いか低いかによって、相手方の対応も異なります。
例えば、不動産の価格が100万円以下の場合と数千万円の場合とでは、自ずと、相手方の対応も異なることになります。
不動産の価格が100万円以下の場合、相手方も比較的容易に応じてくれる可能性があります。(相手方の法定相続分に相当する金額が比較的低い。)
反対に、不動産の価格が数千万円の場合、相手方としては、法定相続分に換算すれば、相当な金額を受取れると考えるのが通常です。
このように、不動産の価格がどれくらいであるのかによって、交渉する側としては、相手方に対するアプローチの仕方(提示する金額など)が異なってきます。
例えば、不動産の価格が数千万円もする場合、交渉する側として、自分がこれまで固定資産税を支払ってきたという事情や、親から引き継いできたという事情を根拠に、自分がすべてを取得し、相手方には、それ相応の金額(法定相続分に相当する金額よりも低い代償金)を支払えればよいと考えるのでは、相手方が協力する可能性は低くなります。もっとも、このことは、相手方がどういう人なのかにもよります。
ポイント2【疎遠な・面識のない・知らない相続人がどういう人か】
疎遠な・面識のない・知らない相続人がどういう人なのかということも、相手方との交渉で、考えておく必要があります。(もっとも、最初から分かりません。)
この場合、交渉する側が自分の意向をやみくもに伝えることは避け、不動産の価格が高いか低いかにかかわらず、最初の手紙文では、慎重に丁寧に、相手方の気持ちを損なうことがないようにした方がよいでしょう。
このことは、そもそも、疎遠な・面識のない・知らない相続人がどういう人なのかが分からないからです。
ポイント3【交渉する人:本人・弁護士・司法書士の資質(能力・判断力)】
交渉する人が、本人・弁護士・司法書士(司法書士は基本的に相手方と交渉ができません。)の場合であっても、相手方と上手く交渉できる資質(能力・判断力)があるかによっても、これらの人の選択を慎重にした方がよいでしょう。このことは、これらの人の選択を誤る場合、交渉の結果に影響を及ぼすことになるからです。
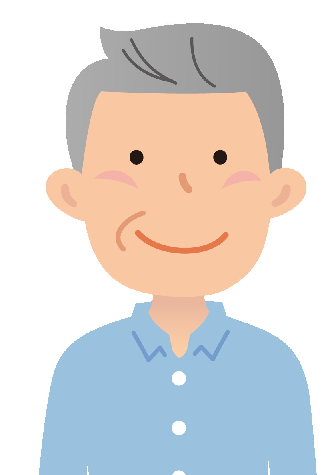
交渉する人が本人(すべて自分で)の場合
交渉する人が本人の場合、手紙文を自分で考え作成するほか、相手方と電話や、直接、会うことで交渉することになりますが、この際の話し方を含めて、相手方の気持や意向を尊重しながら行うことができるのかどうかを考えた方がよいでしょう。そういう意味でも、相手方と交渉する本人の資質(能力・判断力)が重要だと思われます。
相手方との交渉にかかる費用を低く抑えたいのであれば、本人に、文書作成・交渉する資質(能力・判断力)があるということが前提となります。

交渉する人が弁護士の場合
交渉する人が弁護士の場合、相手方との交渉をスムーズに行ってくれるのが、弁護士の重要な資質(能力・判断力)です。
弁護士に交渉を依頼するということは、それ相応の金額を弁護士に支払うことになるからです。不動産の価格がどんなに低い場合であっても、弁護士に交渉を依頼するということは、着手金を含めて最低でも50万円はかかることになります。弁護士にお金を支払って依頼する以上、スムーズに解決してもらいたいと思うことは普通のことだからです。

交渉する人が司法書士の場合
司法書士は、遺産分割の場合、基本的に相手方と交渉ができませんので、司法書士に依頼する場合、どの程度のことをしてくれるのか、依頼内容の費用がどのくらいかかるのかを、よく確認した方がよいでしょう。
また、司法書士に依頼する場合、基本的に、実際、相手方と交渉するのが本人であるため、本人が交渉することができるのかも、よく考えた方がよいでしょう。これができない場合は、弁護士に依頼することになります。
司法書士に依頼する場合、次のことが考えられます。
(1)司法書士の相手方に対するスタンス:本人の前面に立つのか、司法書士が前面に立たず支援だけなのか
(2)相手方への手紙文の作成:どういう手紙文を作成するのか
(3)アドバイス:交渉方法や手続終了までアドバイスをしてくれるのか
ポイント4【手紙文の内容】
- 手紙文の内容については、交渉を弁護士に依頼する場合、弁護士が手紙文を作成し、相手方と交渉してくれますので、弁護士にお任せとなります。
- 相手方との交渉を本人(すべて自分で)が行う場合、本人が手紙文を考え作成し、相手方と交渉します。
- 相手方との交渉を司法書士が行う場合(実際には交渉できない。)、司法書士が手紙文を作成し、本人が相手方と交渉します。
この場合の手紙文の内容について、本人が司法書士とよく相談の上、司法書士に作成してもらいます。本人の意向も考えながら、司法書士が作成してくれます。
具体的な方法:相続登記等の協力要請文書:作成方法・注意点と司法書士への依頼方法
疎遠な・面識のない・知らない相続人に対して、相続登記を司法書士に依頼する場合について、具体的な疑問・質問などを交えて説明します。
【相続登記相談事例②】
私が相談をした司法書士は、疎遠な・面識のない・知らない相続人に対して司法書士が、私の前面に出て行うということを言っていましたが、こういう司法書士に全部お任せしてよいものかどうかを教えてください。
私は、できることなら、依頼者の私が相手方とのやり取りを行わず、もっぱら司法書士にやり取りを行ってもらった方が、楽であり、安心できると思っています。
また、司法書士が前面に立たず、私を支援してくれる場合であっても、次のようなことを司法書士にしてもらえればと思っています。このようにすることで、私も安心して司法書士に依頼すことができますし、相手方にも司法書士という専門家がサポートしているということが分かりますので、相手方も安心できるのではないかと思います。
①司法書士に協力してもらって、手続を進めている旨の文を冒頭に入れてもらう。
②封筒の差し出し人として、私と連名で司法書士事務所名、担当司法書士名を記入する。
③担当司法書士の名刺を同封する。
司法書士のタイプ:疎遠な・面識のない・知らない相続人に対して
司法書士のタイプ:依頼者(本人)の前面に立って行う
依頼者(本人)の前面に立って行うとは、どういうことをするのか、当司法書士事務所では、このようなスタンスを採っておりませんので、詳しく説明することができません。
当司法書士事務所では、次の依頼者(本人)の前面に立たず、あくまでも依頼者(本人)を支援するスタンスを採っています。
費用面で言えば、依頼者(本人)の前面に立って行うスタンスを採る司法書士事務所の費用(報酬)は、比較的高くなると思われます。
司法書士のタイプ:依頼者(本人)の前面に立たず、あくまでも依頼者(本人)を支援する
相談事例②で相談者(本人)が司法書士に依頼する場合に、次のことをしてほしいと考えています。
- 依頼者が相手方とのやり取りを行わず、もっぱら司法書士にやり取りを行ってもらった方が、楽であり、安心できると思っている。
- 次のようにすることで、依頼者も安心して司法書士に依頼すことができ、相手方にも司法書士という専門家がサポートしているということが分かるので、相手方も安心できるのではないかと思っている。
① 司法書士に協力してもらって、手続を進めている旨の文を冒頭に入れてもらう。
② 封筒の差し出し人として、私と連名で司法書士事務所名、担当司法書士名を記入する。
③ 担当司法書士の名刺を同封する。
上記、依頼者の望む内容が、果たして、まったく問題がないのか、交渉結果にどのような影響を及ぼすことになるのか、吉と出るのか凶とでるのかは、やってみなければ分からないことです。しかし、依頼者の望むことを鵜呑みにして行うことは、専門家であれば、よくよく検討する必要があります。
【当司法書士事務所の考え方】
当司法書士事務所の方針について、相談者本人が不安になる理由は、司法書士が前面に立たず、相談者本人が前面に立つことになるので、上手く事が運ぶかどうか不安になるということだと思われます。
交渉にかかる費用を低く抑えたいのであれば、本人が自分で行うことになります。本人に資質(能力・判断力)があれば、問題ありません。もっとも、交渉に際しての方法などは、司法書士がアドバイスしておりますので、それほど心配することはないと思います。
もしも、完全に不安を解消したいのであれば、弁護士に「交渉」を依頼するしかありません。
少なくとも、現段階では、相談者が弁護士に依頼することはないと思いますので、相手方に対する話し方などは、相談者本人の資質(能力・判断力)によることになります。
司法書士が前面に出るという場合、司法書士は、基本的には、説明のみで、「交渉」することができません。例えば、相手と、いくら支払うかについて交渉することができません。
当司法書士事務所の考え方は、前述ように、会ったことも話したこともない相続人がどういう考えを持った人なのか、分からない場合、慎重に対応すべきだと考えます。
最初から「私には専門家(司法書士や弁護士)がついていますよ。」という捉え方をされた場合、相手方がより慎重に、身構える可能性が高くなります。
司法書士事務所名を出すのであれば、交渉がある程度、進展して、相手方との信頼関係がある程度、築けた後にした方がよいでしょう。(例えば、「詳しい内容は、○○司法書士事務所が説明します。」など)
より慎重に考える理由:疎遠な・面識のない・知らない相続人に対して
今から20年以上前でしたら、専門家がついていることも、そう深く考えることはありませんでした。
ですが、現在は、一般の人でも、ネットで調べれば、専門家以上に深堀して知識を得ることができます。そのようなことで、昔よりも現在の人の方が、法律意識・権利意識が高い傾向にあります。
このような法律意識・権利意識の高い人が相手方となる場合、より慎重に対応することが求められます。
相手方が、法律意識・権利意識の高い人かどうかも分からないので、リスクを取らず、慎重に対応した方がよいと思われます。司法書士が前面に出た場合、相手方との交渉では、話しがまとまらないリスクが高まります。
司法書士の立場は、説明を求められたときに、説明だけするのが基本です。交渉することができません。
話しがこじれたときに、交渉するのが弁護士であり、簡裁代理権を持っている司法書士が、説明ではなく、正式に相手方と交渉します。
遺産分割協議の話し合いでは、最初から、司法書士が前面に出ることで、相手方は身構えることになります。こういうことは避けた方が賢明です。
専門家(弁護士や司法書士)であれば、相手方からの手紙に専門家がついていることが分かれば、自分の取り分・相続分を厳密な意味で計算し、それを基準に交渉します。
専門家がついているということは、専門家から有利になるようにアドバイスを受けていると考えるのが普通だからです。
例えば、相談事例①の不動産の価格が100万円(相続人10名)である場合であっても、会ったことも話したこともない相続人にいくら支払ったらよいのか(支払わなくてもよいのか)ということが最大の問題ですが、話しの持って行き方で、数千円で済むのか、数万円かそれ以上になるのかという問題があります。
(この金額を決めることを相手方と司法書士が話すことになれば、それは「交渉」ということになります。)
専門家がついているのであれば、当然、有利な方法で交渉してくるであろうと推測できます。これは、金額に直しますと、本人が数千円で済まそうと考えていると、普通、相手方は考えます。
結果として、数千円で済むとしても、前述のように、慎重に行う必要があります。
という理由からも、最初から、司法書士の名前を出すことで、本人は安心できるかもしれませんが、このことが、かえって相手方を刺激すること、誤解を生じることにもなりかねません。
最初の段階で、誤解を生じてしまいますと、その後の遺産分割の合意が遠くなる可能性が高くなります。
司法書士は、基本的に遺産分割について交渉ができない。
本人としては、専門家の司法書士が前面に出てもらえれば、安心できると思われるかもしれませんが、司法書士は、遺産分割について、基本的には相手方と「交渉」することができません。
遺産分割で相手方と交渉できるのは、弁護士だけです。
ただし、簡裁代理権を持っている司法書士は、140万円以内の事案であれば、本人を代理して相手方と交渉することがきます。
今回の案件では、建物の評価価格が100万円なので、司法書士が相手方と交渉してもよさそうですが、相手方から、いらぬ誤解を生じないようにする必要があります。また、単に100万円を基準に考えてよいのかという問題もあります。
評価価格が100万円だから、この金額が絶対とも、現段階の話し合いでは、言い切れないからです。もし、この金額が絶対だということで交渉した場合、相手方が納得しなければ、遺産分割調停(家庭裁判所)で解決するしかなくなります。そうしますと、解決まで半年以上はかかり、費用も余計にかかることになります。できるだけ、話し合いで解決するという姿勢が大事です。遺産分割調停(家庭裁判所)は、最後の手段だと考えた方がよいでしょう。遺産分割調停(家庭裁判所)となれば、相手方には、最低限、法定相続分に相当する金額を支払うことになります。
相談事例の場合、相続登記に協力してもらうというこちらからの相手方に対するお願いで、あくまでも協議で合意しようとしていますので、「評価価格が100万円だから」という理由や、また、自分が、これまで固定資産税を支払ってきたという事情や、親から引き継いできたという事情を根拠に、自分がすべてを取得し、相手方には、それ相応の金額(法定相続分に相当する金額よりも低い代償金)を支払えればよいという、思いを前面に交渉するのは控えた方がよいでしょう。
前述のように、現在、一般の人の法律意識・知識が高くなっているとは言っても、このこと、簡裁代理権を持っている司法書士が、140万円以内の事案であれば、本人を代理して相手方と交渉することがきる、ときちんと理解できているかどうか不明です。
最初の、この段階で相手方が誤解しますと、その先の遺産分割の話し合いまで影響する可能性があります。
ですから、司法書士が前面に出ることで、司法書士が交渉しているのではないかと誤解されることを避ける意味でも、最初の手紙文では、司法書士の名前を出さない方が賢明だという理由です。
もし、司法書士の名前を出すことで、相手方と交渉のようなことをすれば、報酬もそれなりに高くなります。また、司法書士の名前を出すことで、事が上手く運ぶとも限りません。
司法書士に依頼する場合、あくまでも、司法書士が前面に立たず、本人を支援することに徹し、手紙文の差出人も本人の名だけにした方がよいでしょう。
過去事例:疎遠な・面識のない・知らない相続人がいる場合の相続登記等
不動産(200万円)の相続:相続人15名
依頼者本人の希望:代償金としてではなく、謝礼を支払う。
交渉結果:話し合いで解決(遺産分割協議成立):謝礼を支払う。
預貯金(3,000万円)の相続:相続人6名
依頼者本人の希望:代償金として○○円(法定相続分に及ばない金額)を支払う。
交渉結果:話し合いで解決(遺産分割協議成立):法定相続分に相当する金額で分配
不動産(6,000万円)の相続:相続人10名
依頼者本人の希望:代償金として○○円(法定相続分に及ばない金額)を支払う。
交渉結果:遺産分割協議不成立(相続人2名が同意しない。)
まとめ:疎遠な・面識のない・知らない相続人がいる場合の相続登記等
相続登記等で、疎遠な・面識のない・知らない相続人がいる場合、これらの人に対するアプローチの仕方は、基本的に、慎重に丁寧に行うことが重要です。
相手方との交渉において、本人は、どうしても自分の利益を優先したい傾向がありますが、自分の利益を優先することで、交渉が上手くいかなくなる可能性があります。
遺産分割協議は、話し合いで解決することのため、この話し合いが上手くいかない場合は、遺産分割調停(家庭裁判所)で行うことになります。遺産分割調停では、基本的には、(結果として)法定相続分を基準に分配することになりますので、特に、遺産の額が高額となる場合は、最初から法定相続分を基準に分配することを念頭に置いた方がよいでしょう。
本人自ら交渉できない場合で、専門家に依頼する場合は、お金はかかっても最初から弁護士に依頼するのか、お金を節約するために司法書士に依頼するのか、どういう方針の司法書士に依頼するのか、最初の段階で、明確にした方がよいでしょう。
【参考ページ】
知らない疎遠な相続人が多数のため複雑かつ困難な数次相続登記の方法は?費用は?:相続登記相談
被相続人祖父(疎遠な・面識のない・知らない相続人がいる)・父名義の数次相続登記(相続登記相談)
疎遠な・面識のない・知らない相続人への相続登記等の協力要請文書(手紙文例)
相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。
相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

