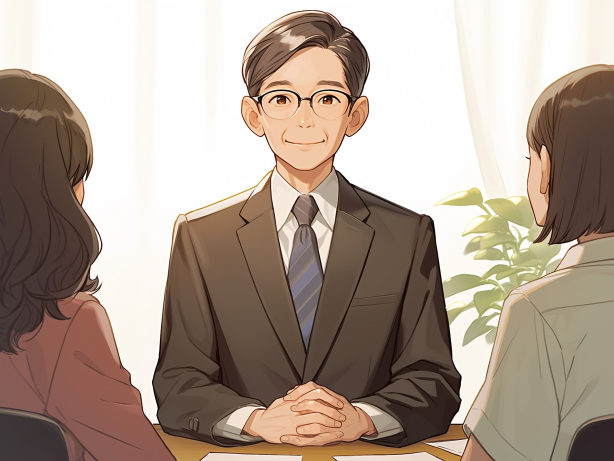疎遠な・面識のない・知らない相続人がいるときの相続登記の手順
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
【相続登記相談(事例)】
(質問)父(持分2分の1)と私(持分2分の1)の共有名義となっている土地・建物があります。
この度、父が亡くなりました。
父には、前妻の子が3名おりますが、この子らの住所が不明です。
父の持分2分の1を私が相続取得したいと考えています。
この場合、どのような手順で、相続登記を行えばよいのかを教えてください。
【被相続人父の遺産:土地・建物】
評価価格:2,000万円
被相続人父の持分:2分の1
被相続人父の遺産:1,000万円

被相続人父の相続人:4名
相談者の子
前妻の子3名

相続登記に必要な書類
事例の場合、基本的に必要となる書類は、次のとおりです。
これらの書類の取得方法については、後述します。
【被相続人(父)】
父の除籍謄本など出生から死亡まで全部
父の「住民票」の除票(本籍・筆頭者の記載のあるもの)
固定資産税納税通知書・課税明細書(評価証明書)
権利証(相続登記で使用する場合もある)
【法定相続人全員:相談者の子と前妻の子3名】
戸籍謄本
住民票・戸籍の附票
遺産分割協議書・印鑑証明書(遺産分割協議が整ったとき)
相続登記の手順
事例の場合の相続登記の基本的な手順は、次のとおりです。
(相談者の子)
前記「相続登記に必要な書類」を取得、用意します。
これにより、前妻の子3名の住所が判明します。
(相談者の子)
前妻の子3名に郵送する手紙文(1回目)を作成します。
前妻の子3名宛てに、手紙文(1回目:説明文書・参考資料と返答書を同封)を郵送します。
(前妻の子3名)
相続についての返答書を返送します。
(相談者の子)
前妻の子3名全員が、「相談者の子」の提案(1回目の手紙文で)に同意したとき、前妻の子3名への手紙文(2回目)と遺産分割協議書を作成し、郵送します。
前妻の子3名全員が、「相談者の子」の提案に同意しないとき
さらに、前妻の子3名全員の同意が得られるような内容の手紙文を作成し、郵送します。
(前妻の子3名)
遺産分割協議書と印鑑証明書を郵送します。
(相談者の子)
登記申請します。
取得する相続書類
まず最初に、「相談者の子」が次の書類を取得します。
【被相続人(父)】
父の除籍謄本など出生から死亡まで全部
父の「住民票」の除票(本籍・筆頭者の記載のあるもの)
【法定相続人全員:「相談者の子」と前妻の子3名】
戸籍謄本
住民票・戸籍の附票
「相談者の子」が「広域交付の方法」で除籍戸籍謄本を取得
「相談者の子」が最寄りの役所(通常、住所地の市区町村役場)に、次の書類と印鑑を持参します。
①運転免許証・マイナンバーカードなど写真付き身分証明書
②認印
③父の氏名・本籍・生年月日が分かるものを持参する。
すでに取得した「父の除籍謄本」がある場合は、これを持参し、これ以外の除籍謄本を取得する。
戸籍課証明係で、次の戸籍除籍謄本を取得します。
①父の出生から死亡までの除籍謄本
②「相談者の子」の戸籍謄本
これらの書類は、「戸籍証明書等の広域交付」の方法で全部取得することができます。
「戸籍証明書等の広域交付」の方法は、次のページでご確認ください。
「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類の取得方法
その他の書類を取得
これらを取得した後、次の書類を取得します。
次の書類は、「戸籍証明書等の広域交付」の方法で取得できません。
それぞれの役所(市区町村役場)に請求(郵送などで)します。
①被相続人(父):「住民票」の除票(本籍・筆頭者の記載のあるもの)
②「相談者の子」:住民票
③前妻の子3名:戸籍謄本と戸籍の附票
【前妻の子3名の「戸籍謄本と戸籍の附票」の取得方法】
被相続人父の除籍謄本の記載内容から、前妻の子3名の「現在の本籍」が判明するまで、役所(市区町村役場)に、戸籍除籍謄本と「戸籍の附票」を請求(郵送などで)します。
「戸籍の附票(住所が記載されている)」を取得できれば、前妻の子3名の住所が判明します。

前妻の子3名の「戸籍謄本と戸籍の附票」を取得できる法律上の正当な理由は、次のとおりです。
前妻の子3名は、被相続人父の相続人であり、「相談者の子」も被相続人父の相続人であるので、「相談者の子」が、相続人を確定させるために、前妻の子3名の「戸籍謄本と戸籍の附票」を取得することは、法律上の正当な理由があるといえます。
前妻の子3名に郵送する手紙文(1回目)を作成
前妻の子3名の住所が判明したので、前妻の子3名に郵送する手紙文(1回目)を作成します。前妻の子3名宛てに、手紙文(1回目:説明文書・参考資料と回答書を同封)を郵送します。
この手紙文では、前妻の子3名が、被相続人父の相続人であること、不動産(土地・建物)の相続登記に協力してほしい旨などを記載します。
手紙文の書き方については、疎遠な・面識のない・知らない相続人への相続登記等の協力要請文書(手紙文例)を参考にしてください。
前妻の子3名に提案する内容
事例の場合、土地・建物の評価価格(とりあえず評価価格で評価)が2,000万円で、被相続人父の持分が2分の1であるので、被相続人父の遺産額として1,000万円とします。
相続人は、「相談者の子」と前妻の子3名であるので、相続人は計4名です。
このことから、相続金額は、1名当たり250万円となります。
代償分割の金額:代償金
「相談者の子」が不動産を取得(被相続人父の持分2分の1)する場合、前妻の子3名に代償金として、それぞれに250万円支払うという内容の遺産分割(代償分割)を提案するのであれば、比較的、前妻の子3名の了解を得られやすくなると思われます。
この金額よりも低い金額を提案するときは、遺産分割が難しくなると思われます。
「相談者の子」が、この金額よりも低い金額を代償金とし、前妻の子3名の了解を得られない場合は、遺産分割調停を申立て、家庭裁判所で解決することになります。
前妻の子3名に郵送する手紙文(2回目)を作成
前妻の子3名全員が、「相談者の子」の提案(1回目の手紙文で)に同意したときは、前妻の子3名への手紙文(2回目)と遺産分割協議書を作成し、郵送します。
前妻の子3名全員が、「相談者の子」の提案(1回目の手紙文で)に同意しないときは、さらに、前妻の子3名全員の同意が得られるような内容の手紙文を作成し、郵送します。
前妻の子3名が同意することになったとき
前妻の子3名への手紙文(2回目または3回目以降)と遺産分割協議書を作成し、郵送します。
前妻の子3名から遺産分割協議書と印鑑証明書を郵送してもらいます。
事例の場合、当司法書士事務所に依頼する場合の相続登記費用
相続登記費用
実費
登録免許税:40,000円
事前・登記事項確認2通:662円
完了・登記事項証明書2通:980円
郵送料:前妻の子3名への郵送料、10,000円(仮)
司法書士報酬は、
基本報酬:55,000円(相続人5名まで)
追加報酬
手紙文1回目の作成と郵送作業:10,000円
手紙文2回目の作成と郵送作業:10,000円
司法書士報酬には、遺産分割協議書・相続関係説明図の作成料が含まれます。
実費:41,642円+10,000円(郵送料)
報酬:75,000円+7,500円(消費税)
合計:134,142円(約)
まとめ:疎遠な・面識のない・知らない相続人がいるときの相続登記の手順
疎遠な・面識のない・知らない相続人がいるときの相続登記の手順は、次のとおりです。
- 被相続人と相続人の相続登記に必要な書類を取得、用意する。
- 疎遠な・面識のない・知らない相続人に対する手紙文(1回目)を作成し、郵送する。
- 疎遠な・面識のない・知らない相続人が遺産分割の提案内容に同意したときは、遺産分割協議書を作成して郵送する。
- 提案する遺産分割の内容は、疎遠な・面識のない・知らない相続人が同意しやすい内容とする。
- 疎遠な・面識のない・知らない相続人が同意しない場合は、遺産分割調停を申し立てる。
相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。
相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム