- 法定相続登記をした後の所有権更正登記:登記権利者が単独で申請できる場合(概要)(令和5年4月1日から単独申請が可能)
- 相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。
法定相続登記をした後の所有権更正登記:登記権利者が単独で申請できる場合(概要)(令和5年4月1日から単独申請が可能)
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
以下の内容については、次の法務省のページを参照してください。
令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達:法務省民二第538号令和5年3月28日民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)
登記権利者(相続人)が単独で申請できる条件
法定相続登記をした後、所有権更正登記を、登記権利者が単独で申請できる場合とは、法定相続分で相続登記がなされた後、次の4つの場合に限って、登記権利者となる相続人(相続人以外の者はできない)が単独で申請できる場合のことをいいます。
法定相続分での相続登記は、次のページを参考にしてください。
法定相続分での相続登記の方法
共同相続人1人からの相続登記の方法(法定相続分で遺言書で)
債権者代位による相続登記
登記権利者(相続人)が単独で申請できる4つの場合
登記権利者(相続人)が単独で申請できるのは、次の4つの場合に限られます。
(1)遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
(2)他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
(3)特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
(4)相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
所有権更正登記申請:登記権利者(相続人)の単独申請のポイント
これら4つの場合は、いずれも、次の条件を満たす必要があります。
(1)法定相続分で相続登記がなされている。
(2)申請できる登記権利者は、相続人のみ。
登記権利者となる人が相続人であること。登記権利者が第三者となる場合は、単独申請ができない。
(3)登記上の利害関係人が存在しない(存在する場合は、第三者の承諾書が必要)。
従来は、これら4つの場合に、登記権利者となる相続人が単独で申請できず、登記義務者となる他の相続人との共同申請で行われていました。
この(他の相続人との共同申請で行う)場合、他の相続人からの権利証・印鑑証明書・委任状などに実印押印が必要なことから、登記権利者名義とすることが難しい場合がありました。
そこで、令和5年4月1日から、これら4つの場合に限って、登記権利者となる相続人が単独で申請できるようにしたことで、従来よりも、比較的容易に登記権利者名義とすることが可能となりました。
ただし、登記権利者となる相続人が単独で申請できる場合であっても、登記上の利害関係を有する第三者がある場合は、従来どおり、この第三者の承諾(第三者の印鑑証明書付き承諾書が必要)がなければ、登記権利者となる相続人が単独で申請できません。これについては、後述します。
法定相続分での相続登記とは
民法第900条及び第901条の規定により算定した法定相続分に応じてなされた相続による所有権の移転の登記のことをいいます。
民法(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
民法 | e-Gov法令検索
登記権利者(相続人)が単独で申請できる4つの場合:登記原因・登記原因証明情報・登記記載例
次に、登記権利者(相続人)が単独で申請できる4つの場合の、登記原因・登記原因証明情報・登記記載例について説明します。
(1)遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
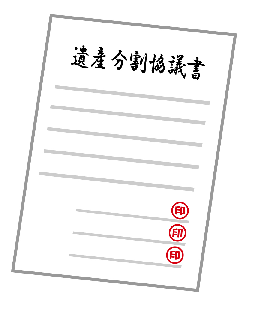
これについては、次の二通りの場合が考えられます。
● 法定相続分での相続登記をした後、遺産分割協議(調停・審判)が成立(確定)した場合
● 法定相続分での相続登記をした後、この登記の前、すでに、遺産分割協議(調停・審判)が成立(確定)していた場合
登記原因、日付、登記原因証明情報:遺産分割協議(調停・審判)
遺産分割協議による場合
〇年〇月〇日遺産分割
登記原因:遺産分割
日付:協議が成立した日
登記原因証明情報:遺産分割協議書・他の相続人の印鑑証明書
遺産分割調停による場合
〇年〇月〇日遺産分割
登記原因:遺産分割
日付:調停が成立した日
登記原因証明情報:遺産分割調停調書の謄本
遺産分割審判による場合
〇年〇月〇日遺産分割
登記原因:遺産分割
日付:審判が確定した日
登記原因証明情報:遺産分割審判書謄本(確定証明書付)
登記記載例:遺産分割協議(調停・審判)による所有権更正登記
法定相続登記を兄・妹の法定相続分(各2分の1)で登記した後、遺産分割協議が成立し、兄が不動産を単独で相続取得した場合の登記記載例です。

遺産分割による所有権更正登記の方法:具体例
次のページを参考にしてください。
法定相続登記後の遺産分割による所有権更正登記【最新】
(2)他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
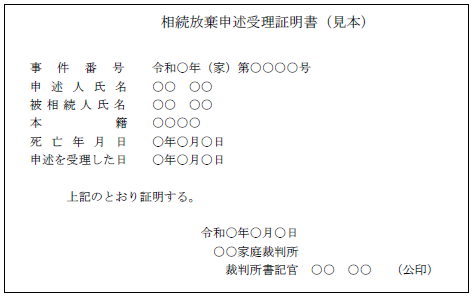
これについては、次の二通りの場合が考えられます。
ここでいう「相続の放棄」とは、家庭裁判所での相続放棄のことをいいます。
● 法定相続分での相続登記をした後、他の相続人が相続放棄をした場合
● 法定相続分での相続登記をした後、この登記の前、すでに、他の相続人が相続放棄をしていた場合
登記原因、日付、登記原因証明情報:他の相続人の相続放棄
相続放棄による場合
〇年〇月〇日相続放棄
登記原因:相続放棄
日付:家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された日
登記原因証明情報:相続放棄申述受理証明書、相続を証する公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合は、これに代わるべき情報)
登記記載例:他の相続人の相続の放棄による所有権更正登記
法定相続登記を兄・妹の法定相続分(各2分の1)で登記した後、妹が相続放棄をしたため、兄が不動産を単独で相続取得した場合の登記記載例です。

相続放棄による所有権更正登記の方法:具体例
次のページを参考にしてください。
法定相続登記後の相続放棄による所有権更正登記【最新】
(3)特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
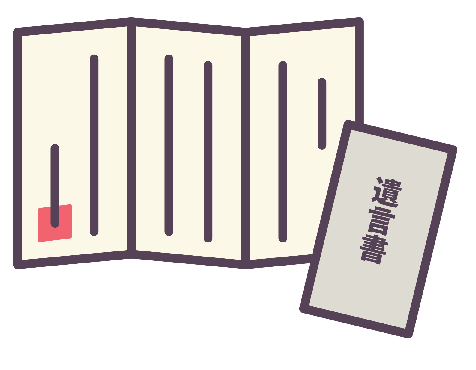
これについては、次の場合が考えられます。
● 法定相続分での相続登記をした後、他の相続人に対して特定の不動産を相続させる旨の遺言書があった場合
登記原因、日付、登記原因証明情報:特定財産承継遺言(遺言書があった場合)
特定財産承継遺言による場合(遺言書があった場合)
〇年〇月〇日特定財産承継遺言
登記原因:特定財産承継遺言
日付:特定財産承継遺言の効力が生じた日
登記原因証明情報:遺言書(公正証書遺言書、登記所保管制度の遺言書のほか家庭裁判所の検認手続を経た自筆証書遺言書)
特定財産承継遺言による場合(遺言書があった場合)
法務局から登記義務者に対し、所有権更正登記の申請があった旨が通知されます(改正不登規則第183条第4項)。これは、申請書類の調査完了後(登記完了前)、速やかに登記義務者の登記記録上の住所に宛てて通知書が発送されます。この場合、通知書が発送された後、登記義務者からの中止要請などがあった場合であっても、登記手続の処理が中止や停止することがありません。
登記記載例:特定財産承継遺言による所有権更正登記
法定相続登記を兄・妹の法定相続分(各2分の1)で登記した後、不動産を兄に相続させる旨の遺言書があったことにより、兄が単独で相続取得した場合の登記記載例です。

特定財産承継遺言による所有権更正登記の方法:具体例
次のページを参考にしてください。
法定相続登記後の特定財産承継遺言による所有権更正登記【最新】
(4)相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
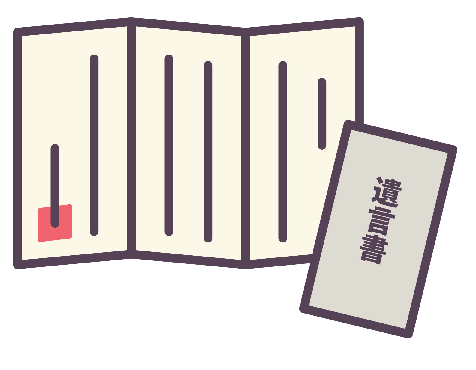
これについては、次の場合が考えられます。
● 法定相続分での相続登記をした後、他の相続人に対して特定の不動産を遺贈する旨の遺言書があった場合
登記原因、日付、登記原因証明情報:相続人が受遺者である遺贈(遺言書があった場合)
相続人が受遺者である遺贈の場合(遺言書があった場合)
〇年〇月〇日遺贈
登記原因:遺贈
日付:遺贈の効力が生じた日
登記原因証明情報:遺言書(公正証書遺言書、登記所保管制度の遺言書のほか家庭裁判所の検認手続を経た自筆証書遺言書)
相続人が受遺者である遺贈による場合(遺言書があった場合)
法務局から登記義務者に対し、所有権更正登記の申請があった旨が通知されます(改正不登規則第183条第4項)。これは、申請書類の調査完了後(登記完了前)、速やかに登記義務者の登記記録上の住所に宛てて通知書が発送されます。この場合、通知書が発送された後、登記義務者からの中止要請などがあった場合であっても、登記手続の処理が中止や停止することがありません。
登記記載例:相続人が受遺者である遺贈による所有権更正登記
法定相続登記を兄・妹の法定相続分(各2分の1)で登記した後、不動産を相続人の兄に遺贈する旨の遺言書があったことにより、兄が単独で相続取得した場合の登記記載例です。

遺贈による所有権更正登記の方法:具体例
次のページを参考にしてください。
法定相続登記後の遺贈による所有権更正登記【最新】
登記上の利害関係を有する第三者がある場合
● 登記上の利害関係を有する第三者がある場合、第三者の承諾がなければ、所有権更正登記を申請することができない。
● 登記上の利害関係を有する第三者がある場合、第三者の承諾があれば、所有権更正登記を申請することができる。
登記上の利害関係を有する第三者とは
登記上の利害関係を有する第三者とは:登記されている抵当権者、(仮)差押権者など
登記上の利害関係を有する第三者とは、例えば、次のような事例です。
法定相続分で相続登記した後、他の相続人の持分について、抵当権設定登記や(仮)差押登記などがあった場合、これらが登記されている抵当権者や(仮)差押権者のことを「登記上の利害関係を有する第三者」といいます。


この事例のように、法定相続分(兄・妹各2分の1)で相続登記した後、他の相続人(妹)の持分について、抵当権設定登記や(仮)差押登記などが登記されている場合、「登記上の利害関係を有する第三者」である抵当権者や(仮)差押権者などが、承諾書(印鑑証明書付き)を提供してくれない場合は、所有権更正登記を申請できないことになります。
反対に、抵当権者や(仮)差押権者などが、承諾書(印鑑証明書付き)を提供してくれる場合は、所有権更正登記を申請できることになります。
この承諾書(印鑑証明書付き)を添付して申請し、所有権更正登記がなされた場合、抵当権や(仮)差押などは、登記所の職権で朱抹されることになります。
通常、実際に、この承諾書を提供してもらうことは、難しいといえます。
まとめ:法定相続登記後の所有権更正登記:登記権利者(相続人)が申請できる場合
従来、相続の場合の所有権更正登記は、登記権利者となる相続人が単独で申請できず、登記義務者となる他の相続人との共同申請で行われていました。
この(他の相続人との共同申請で行う)場合、他の相続人からの権利証・印鑑証明書・委任状などに実印押印が必要なことから、登記権利者名義とすることが難しい場合がありました。
そこで、令和5年4月1日から、これら4つの場合に限って、登記権利者となる相続人が単独で申請できるようにしたことで、従来よりも、比較的容易に登記権利者名義とすることが可能となりました。
ただし、登記上の利害関係を有する第三者がいるときには、注意が必要です。
相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。
相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

